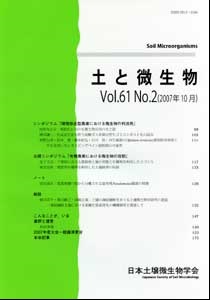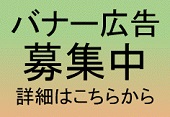学会誌「土と微生物」最新号
- 79-2
- 79-1
- 78-2
- 78-1
- 77-2
- 77-1
- 76-2
- 76-1
- 75-2
- 75-1
- 既刊号
79巻2号(2025年10月発行)
シンポジウム
竹下 典男:細菌と糸状菌の空間的・代謝的相互作用中原 浩貴・染谷 信孝・村上 理都子・冨髙 保弘・松山 桃子・前田 陽佑・窪田 昌春:植物の健康に役立つ微生物 ―植物病害虫から植物を守る微生物―
総説
藤谷 拓嗣:亜硝酸酸化細菌研究の最前線大矢 朱莉・宇佐見 俊行:日本で突然発生したレタス黒根病,その病原菌の性状について
解説
Katsuki Adachi, Tooru Kobayashi, Takayuki Suzuki, Toru Kosugi:Sweet potatoes’ relationship with arbuscular mycorrhizal fungi and endophytic diazotrophic bacteria: A co-inoculation experiment光延 聖・和穎 朗太:土壌団粒の孔隙ネットワークによって制御される微生物N2O還元:1粒観察から見えてきた特異な微小環境
日本土壌微生物学会2025年度大会講演要旨
79巻1号(2025年4月発行)
巻頭言
大友 量:家族農業と主婦と土壌微生物特別企画
今泉(安楽) 温子:根粒共生促進根圏微生物による根粒共生能力の促進 ~環境負荷低減とマメ科作物の収量増収を可能にする取り組みYong Guo, Hiroyuki Ohta, Tomoyasu Nishizawa:Mitigating Global Warming in Agriculture: Recent Highlights on Cooling the Earth by Soil Microorganisms
多胡 香奈子・染谷 信孝:日本土壌微生物学会70 周年記念特別企画 「土と土壌微生物研究のフロンティア」を終わるにあたって
シンポジウム
磯井 俊行:持続的農業と作物共生微生物竹本 大吾:植物と微生物の生存競争 ―物質を介した両者の相互作用―
染谷 信孝・澤田 宏之・諸星 知広:Pectobacterium―日本産軟腐病菌株の再解析
原著論文
肥後 昌男・立脇 祐哉・橋本 航・佐々木 洋平・邱 琬貽・磯部 勝孝:黒ボク土に立地したトウモロコシ栽培体系での異なる耕起処理が 土壌細菌の群集構造と多様性に及ぼす影響肥後 昌男・立脇 祐哉・橋本 航・佐々木 洋平・邱 琬貽・磯部 勝孝:黒ボク土に立地したトウモロコシ栽培体系での異なる耕起処理が 土壌細菌の群集構造と多様性に及ぼす影響 ―第2 報:トウモロコシ根内の比較―
Sato Erika, Hiroyuki Sekiguchi, Masato Kawabe, Shigenobu Yoshida:Detection and quantification of Diaporthe destruens from soil using real-time PCR with a novel TaqMan probe
こんなことが、いま
多胡 香奈子・大矢 朱莉・松尾 百華・三井 彩花・加藤 理紗子・鈴木 琉太:「日本土壌微生物学会2024年度大会」開催報告・「日本土壌微生物学会 2024 年度大会」 学生ポスター賞受賞者の声から78巻2号(2024年10月発行)
特別企画
福永 省吾・岡崎 伸:ダイズRj遺伝型と根粒共生原 沙和・板倉 学:根粒菌による温室効果ガス(N2O)の削減技術の現在 -N2O還元根粒菌の新たな可能性を探る-
シンポジウム
伊藤 英臣:土壌に特異的に優占する難培養微生物群のバイオリソース拡充藤井 一至:持続的農業と土壌の健康の実現に向けた土壌生成・劣化メカニズムの解明
原著論文
Dina Istiqomah, Tri Joko, Masahiro Umehara, Naoko Kanuma, Ryota Moriuchi, Hisae Hirata, Naoto Ogawa, Shinji Tsuyumu:LfaR, a LacI Transcriptional Regulator, is Involved in Phytopathogenesis of Dickeya dadantii 3937前上門 陽・田場 聡・佐藤 裕之・関根 健太郎・諏訪 竜一・西平 守司:サクヤアカササゲ種苗腐敗病(新称)の発生と ベノミルによる種子消毒および生物防除の有効性の検討
書評
妹尾 啓史・早津 雅仁・平舘 俊太郎・和穎朗太 編:「朝倉農学体系9 土壌学」日本土壌微生物学会2024年度大会講演要旨
78巻1号(2024年4月発行)
追悼
平野 和爾・宍戸 雅宏:飯田 格先生を偲ぶ巻頭言
多胡 香奈子:「土と微生物」約 70 年分イッキ読み!特別企画
川原田 泰之:根粒共生で機能するBradyrhizobium 属根粒菌の菌体外多糖シンポジウム
加藤 広海:土壌環境の細菌叢は移植できるのか?竹内 香純:根圏における植物保護細菌の制御
原著論文
Silvio Yoshiharu Ushiwata, Ayana Kawashima, Hiroyuki Oshima, Taku Kato, Miwa Yashima, Kazuyuki Inubushi:Effects of land-use and organic fertilization on soil enzyme in a farmer’s fieldsKatsuki Adachi, Takayuki Suzuki:Interaction effect between inoculations of Pantoea agglomerans and pathogenic fungus Fusarium oxysporum on the growth of sweet potato in a pot experiment
書評
齋藤雅典 著:「もっと菌根の世界 知られざる根圏のパートナーシップ」こんなことが、いま
宍戸 雅宏・鈴木 ちはる・中村 美輝・檀上 武志・前田 陽佑:「日本土壌微生物学会2023年度大会」開催報告・「日本土壌微生物学会 2023 年度大会」 学生発表賞受賞者の声から77巻2号(2023年10月発行)
特別企画
大林 翼・Nobuhiro Luciano Aoyagi・山崎 俊正・多胡 香奈子・早津 雅仁:農耕地土壌における硝化による温室効果ガス一酸化二窒素(N2O)の発生とその対策 ―硝化制御によるN2O発生抑制剤開発の基盤構築―原 新太郎・圷 ゆき枝・鈴木 倫太郎・ 早津 雅仁・ 多胡 香奈子:土壌メタゲノム情報から脱窒関連酵素の構造的多様性を明らかにする ―脱窒制御剤の開発に向けて―
菅野 学・玉木 秀幸:農業用微生物資材の研究開発動向のミニレビュー:ブレイクスルーに向けた13の取組み
シンポジウム
犬伏 和之:土の養分運搬から地球環境にまで働いている土壌微生物日本土壌微生物学会2023年度大会講演要旨
77巻1号(2023年4月発行)
追悼
金澤 晋二郎・横山 和平:丸本卓哉先生を偲んで巻頭言
豊田 剛己:土壌微生物学研究への大いなる追い風特別企画
新宮原 諒・中島 泰弘・和穎 朗太:土壌試料における総N2O 還元速度の定量伊藤 虹児・和穎 朗太:土壌微生物群集構造を支配する土壌環境の不均質性に関するミニレビュー:微生物ハビタットとしての土壌を捉えなおす
シンポジウム
野見山 孝司:サツマイモ基腐病に対する苗床の土壌還元消毒による防除技術の開発大久保 智司・青木 裕一:土壌由来の温室効果ガス削減に向けた市民科学による微生物探索
原著論文
森本 晶・伊勢 裕太・大友 量・高田 裕介:λDNAとリアルタイムPCR を用いた土壌DNA抽出効率の評価こんなことが、いま
76巻2号(2022年10月発行)
特別企画
染谷信孝:日本土壌微生物学会 70 周年記念特別企画「土と土壌微生物研究のフロンティア」について南澤 究:温室効果ガス削減と土壌微生物学
シンポジウム
佐伯 雄一:環境傾度によるダイズ根粒菌の群集生態に関する研究九町 健一:窒素固定放線菌Frankia の分子遺伝学
門馬 法明:土壌微生物の力を活用した土壌還元消毒法
唐澤 敏彦:緑肥を利用した減肥・土づくりとそれに役立つ土壌微生物の働き
原著論文
竹腰 恵・池永 誠・富濱 毅・野口 勝憲・境 雅夫:焼酎蒸留残液および化学合成殺菌剤による浸漬処理がジャガイモの種イモ共存細菌叢に与える影響日本土壌微生物学会2022年度大会講演要旨
76巻1号(2022年4月発行)
追悼
宍戸 雅宏・松本 直幸:鈴井孝仁先生を偲んで巻頭言
宍戸 雅宏:土壌微生物と宇宙農業日本農学賞受賞論文
南澤 究:窒素循環を担う植物共生微生物シンポジウム
李 哲揆:様々な野菜を安定生産に導く微生物総説
染谷 信孝・諸星 知広・吉田 重信:Bacillus thuringiensis―微生物殺虫剤からポリバレント資材へこんなことが、いま
75巻2号(2021年10月発行)
追悼
犬伏和之・Agnes Tirol Padre・伊藤 治・齋藤雅典・土屋健一・安達克樹:渡邊 巌先生を偲んでシンポジウム
沢田こずえ・渡邉哲弘・舟川晋也:「ミニマム・ロスの農業」の規範となる自然生態系および伝統的農業生態系土壌における炭素・養分循環の解明妹尾啓史・増田曜子・伊藤英臣・白鳥 豊・大峽広智・Xu Zhenxing・山中遥加・石田敬典・高野 諒・佐藤咲良・Shen Weishou:水田土壌における鉄還元菌窒素固定の学術的基盤解明と低窒素農業への応用:低炭素社会の実現を目指して
浅川 晋:日本人の主食 お米の生産を支える微生物
原著論文
龍田典子・居石優子・古賀夕貴・坂本唯乃・三谷果穂・阿部紘乃・上野大介・染谷 孝:阿蘇地域で生産される野草堆肥およびその施用土壌等における拮抗菌の分布と性状日本土壌微生物学会2021 年度大会講演要旨
書評
田中治夫 編著,村田智吉 著:「土壌環境調査・分析法入門」犬伏和之,白鳥 豊 編:「改訂 土壌学概論」
75巻1号(2021年4月発行)
巻頭言
染谷信孝:今こそ学会誌による情報発信をシンポジウム
小寺俊丞・菱池政志・小松 健・有江 力:エンドウ萎凋病菌の特異検出から見えてきたこと太田寛行・西澤智康:土壌微生物と気候変動
原著論文
馬場隼也・平 英敏・冨樫 智・犬伏和之:シアノバクテリアおよび石膏を用いたリーチングに代わる塩類土壌修復の検討立脇祐哉・肥後昌男・磯部勝孝:南関東での冬作物管理の違いや耕起の有無が後作トウモロコシに感染するアーバスキュラー菌根菌の群集構造に及ぼす影響
Shigenobu Yoshida, Tomomi Sugiyama, Masako T. Noguchi, Keiko T. Natsuaki, Hiroshi Sakai, Akiko Furusawa, Keisuke Hoshino, Kentaro Ikeda: Creation of a dose-response curve (DRC) pattern of soils against Verticillium wilt of Chinese cabbage
斎藤宏二郎・長野紀章・安樂 遼・山崎智美・野村奏史・吉田重信:ブロッコリー根こぶ病におけるDRC 作成法の省力化および圃場の発病ポテンシャル評価への応用
書評
染谷 孝 著:「人に話したくなる土壌微生物の世界」斎藤雅典 編著:「菌根の世界」
こんなことが,いま
東條元昭・市川桂菜:「日本土壌微生物学会2020年度大会」開催報告バックナンバー
全ての記事がJ-Stageにて公開されています。※最新号の原著論文,学会シンポジウム論文の閲覧には,別途会員のみに通知するIDとパスワードが必要です。